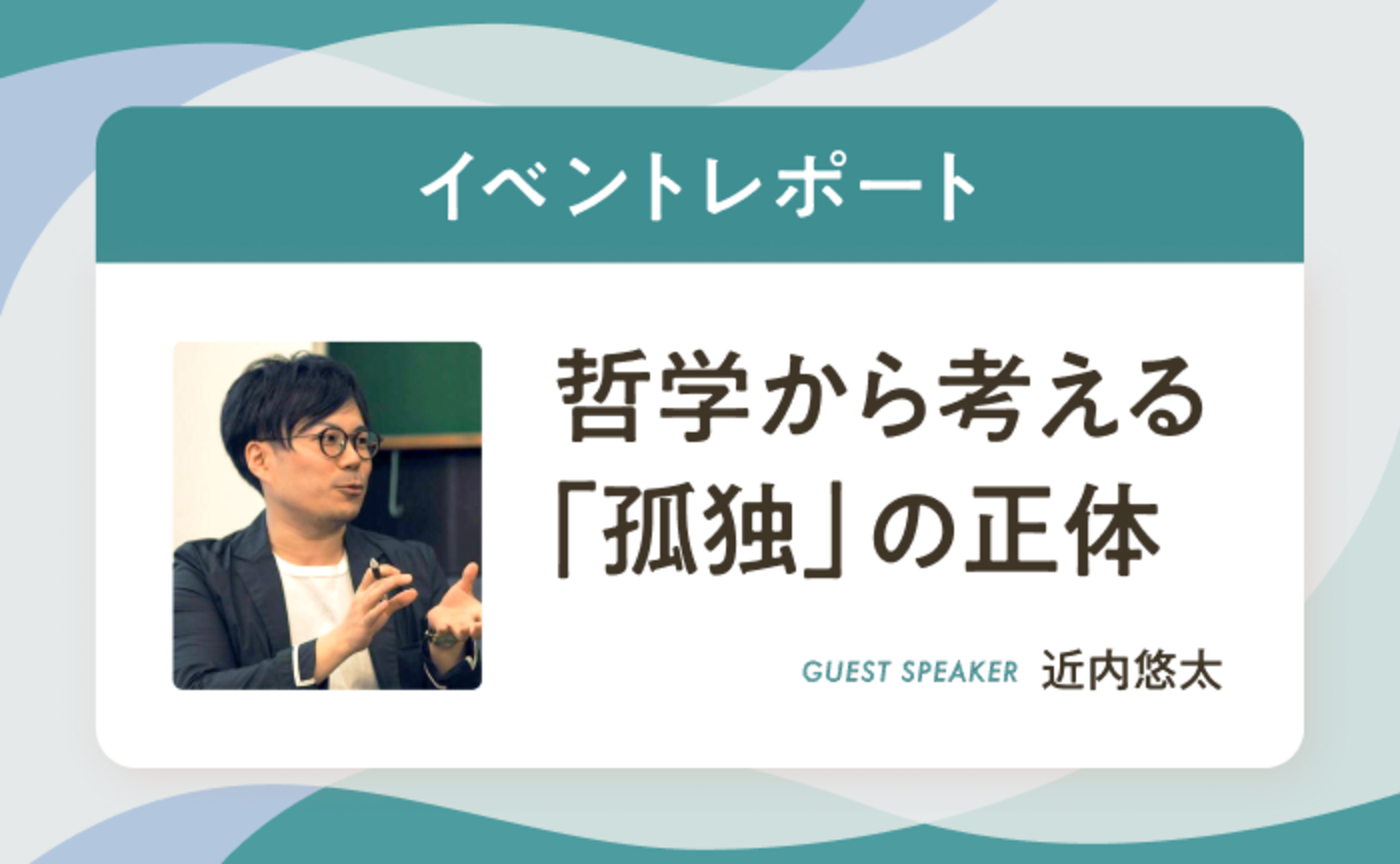フライヤーが主催するオンラインコミュニティflier book laboでは、さまざまな会員限定サービスを提供しています。その魅力をちょっとだけ体験していただける無料のランチタイムセッションが、2025年3月18日に開催されました。
ゲストスピーカーは、オンライン講座「flier book camp」で講師を務めてくださる近内悠太さんです。近内さんが4月より担当する講座は、題して『人生を味わいきるための孤独論〜心を整える哲学の部屋〜 』。
今回のセッションでは、株式会社フライヤーで「flier book camp」企画運営を担当する久保彩のファシリテーションのもと、プログラムの内容を先取りしてご紹介いただきました!
【スピーカー】
教育者・哲学研究者 近内悠太 氏
株式会社フライヤー 執行役員CCO 久保彩 氏
▼セミナーでご紹介した実践講座の詳細・申込みはこちら(3/25〆切)
▼要点
・孤独をなくす、100%否定するのではなく、いかに孤独に抗うか、孤独は自分にとって何を意味しているのかを考える。
・これに価値がある、こうすれば幸せという定義がない現代では、自分にとって何が大切かを理解するのが大事になる。
・本を通じて共通言語を揃えることで初めて、自分と相手の違いについて理解できる。
「孤独」に向き合うことで見えてくるもの
久保彩氏(以下、久保):近内さんの講座は今回で10回目ですが、これまで利他やセルフケア、言語化力、空気など様々なテーマを取り上げていただきました。今回、「孤独」というテーマを選択したのはなぜなのでしょうか。
近内悠太氏(以下、近内):孤独は自分の内側にグッと入っていくテーマなので、僕の講座にぴったりなテーマだと思っています。あるテーマについて深く考えていくと、自分がどんな人生を送ってきたのか、何を考えていて、そのテーマからどんな言葉が連想されるのかなど、自分自身が見えてくるんです。
久保:過去の近内さんの講座を受講された方の声を見てみると、「Day1からDay4までが一つの物語のように展開し、最後には必ず近内さんが見事な結末へと導いてくれる」という声が寄せられていますが、近内さんにとってはどういった場所になっているのでしょうか。
近内:今回のテーマである「孤独」とも結びついてくるのですが、現代を生きる我々に圧倒的に足りていないのは「即興性」だと思っています。僕の講座では毎回四冊のテーマ書籍を設定しているのですが、講座の展開を事前に完璧に計画しているのではなく、「この本の後にこの本をみんなで読むと面白そう、読んでみたい」という予感で選んでいます。この四冊を通してこういうことが見えてきた、と僕が見ているものを共有するのではなく、四ヶ月間を通して参加者の一人ひとりが「だからこの四冊だったんですね」とその人なりの意味が見えてくる。講座の中で参加者のどなたかがたまたま言ったことに対して皆が反応し、それについて皆で考えようとなる。いつもそういう即興性によって導かれた時間になるんです。講座で同じ時間を共にする価値は、そういった予想外、想定外から生み出されるものを楽しむところにあると思っています。計画は頭でするものですが、予感というのは「予め感じる」ということですから、心で起こるものです。
久保:「即興性」と「孤独」が結びついているということですが、どういった繋がりがあるのでしょうか。
近内:例えば、たまたま言ったことに対して、相手が面白いと言ってくれたら繋がった感覚になりませんか?やはり予定されていた合意は面白くなくて、予定されていなかった合意、計画外の共感だからこそ、わかってもらえた感覚になると思います。つながるはずがなかったのに、つながった、というふうに。
久保:なるほど。本日参加の皆さんからは、「孤独ってネガティブですか?」「孤独な時間も必要なのでしょうか?」など様々な問いかけをいただいています。
近内:もし世界から孤独が一切なくなったら、どんな世界が見えるか考えてみていただきたいのですが、僕はそこではまず芸術が消えると思っています。孤独がなかったら自分の内なるエネルギーを外部へとひらく必要がなくなりますよね。僕らにとって大切なものは、痛みや孤独に裏打ちされていると思います。だから、孤独をなくす、100%否定するのではなく、いかに孤独に抗うか、孤独は自分にとって何を意味しているのかを考えていきたいと思っています。孤独が、僕らをどこか未知の場所へと導いてくれる。そんなふうに感じています。
誰かと一緒だからこそ、孤独に向き合える
久保:自分が孤独を感じた経験を思い出してみて、それぞれの解釈を共有し合うことで、ネガティブなイメージだった孤独が、もう少し繊細な言葉になっていきますね。
近内:そうですね。参加者の皆さんと一緒に話していく中で、孤独について新たな側面が見えてきたら面白いなと思っています。僕の講座はインプットでもアウトプットでもなく、自分について理解する時間だと思います。自分一人で考えていると気づかないけれど、他の人が語るのを聞くことで初めて、自分が何を思っていたか輪郭がはっきりするんですね。だからインプットでもアウトプットでもない。自分のことが分かるってこと。それって楽しくないですか?
久保:四冊の本を通じていくつかの孤独の定義に触れながら、そこに自分や他者の経験を掛け合わせて見ていくと、「あれはそういう意味の孤独だったんだ」「あの時感じていた孤独はちょっと違ったのかもしれない」など、自分の中になかった孤独の定義についてリアルに感じていきますね。
近内:こういうレッスンは、本当に今大事だと思っています。現代はこれに価値がある、こうすれば幸せという固定の定義がないんですね。例えば自分にとって価値があると思っていたものがいざ手に入った時に、実は何の価値もなかったと気づいたら、我々は生きる心地を失うと思うんですよね。だから、自分の中に降りて行って、自分が大切だと思うものに気づく、世の中や自分にとって価値がないと思っていたものが、実は自分にとってとても価値があるものだったと気づくことは切実な作業だと思います。そしてまさにこの作業自体が孤独なのです。だって、「これが正解だよ」と言って誰かが与えてくれるものではないからです。自分自身で、独りでそれを掴まなきゃいけない。でも、孤独や自分にとって大切なものについて必死に考える仲間がいれば、自分一人ではないと思えて安心しますよね。自分の中にある「価値観」にダイブするのは独りでやらなきゃいけないけど、その同じプロセスを横並びでやっているメンバーがいればちょっと心強い。だから講座では、孤独に向き合うのは一人ひとりでやって、自分の感覚を言葉にしていくのを皆で一緒にやっていく。皆で孤独に向き合っている連帯感を感じられると思います。
4冊の本を共通言語に、孤独について語り合う
近内:なぜ本を四冊読むかというと、我々は言葉が通じていると思っているだけで、実は全く通じていないからです。例えば、孤独という言葉に対しても、一人ひとり全く違うものを描いていると思うんですね。孤独に関する四冊の本を読むことで、ある程度共通言語が揃うからこそ、自分と相手の何が違うかが理解できるようになると思います。他者と一緒に考えるためには、言葉はある程度揃っていなければならない。そのための四冊なのです。
久保:哲学の考え方をベースに議論するとなると、前提知識のばらつきが気になったり、知識がないと躊躇したり、知識がある人が物足りなく感じたりということが起きがちだと思います。近内さんの講座では、孤独について言葉にできていない状態のまま来ても安心ですね。
近内:そうですね。もし四冊全部読んだことがある方でも、一ヶ月ごとにこの順番で読んでいくとまた違った経験になると思います。三冊目の本と同じことが実は一冊目にも書いてあった、一冊目でピンと来なかったことが二冊目三冊目を読むとよくわかった、孤独について論じる人たちはこういう点を共通して言っているんだと気づくことがあると思います。
久保:今回取り上げる本について改めてご紹介いただいても良いでしょうか。
近内:DAY1の『孤独と不安のレッスン 』は初期設定、入り口として入りやすい本として選んでいます。今回のメインはDAY2の『「待つ」ということ 』、DAY3の『悲しみの秘儀 』になるかな。そして孤独についての輪郭が見えてきた中で最後に読むのが、DAY4の『星の王子さま 』ですね。毎回最後に文学作品をみんなで読むのですが、DAY1〜3で共通言語を揃えた上で、最後に自分がどう感じたかを考えてもらいたいという思いがあります。だから僕の考えた講座の趣旨や何が言いたかったかはおまけ的なもので、自分自身が何を感じて何が見えたのかが最も大事だと思っています。むすんでひらいて。共通言語を「むすぶ」ための三冊と、それをもう一度「ひらく」ための物語を一冊。
久保:孤独とは何か、近内さんが答えをすでに持っているのではなく、自分自身の定義に落としていくのですね。
近内:僕もいち受講生と同じで、講座の最後でようやく「自分にとってはこの4ヶ月間がこういうことだったとわかりましたが、皆さんはどうですか?」と背中を見てもらうような形でやっている感覚ですね。
久保:生成系AIが発達して、簡単に手に入る、出来上がった答えだけを受け取ることに慣れつつあったり、自分の中の感覚を忘れて世の中の言葉だけ追いかけるような自分になってしまったりする私たちにとって、ますます重要な体験になりそうですね。
近内:そうですね。その文脈で言うと、現代で即興性の他にもうひとつ足りていないのが「心底納得する」ことだと思います。生成系AIが言葉を出してくれたとしても、それに納得できないとなったら結局自分で考えるしかないですよね。自分が何を感じていて、何を考えていて、何を大切にしているのかを心底納得するためには、自分の体と頭と心を使ってやるしかないと思います。一人ではやりづらいと思うので、講座ではそれを皆でやっていきたいと思っています。
久保:ありがとうございます。哲学に興味がある方はもちろん、哲学書ではなく非常に読みやすい本を取り扱う講座なので、本を読んで誰かと対話してみたい方にもおすすめです。本を読みながら自分自身で言葉を作っていく楽しさを味わっていただけたら嬉しいです。
▼セミナーでご紹介した実践講座の詳細・申込みはこちら(3/25〆切)
▼セミナー全編はこちらから💁
近内悠太(ちかうち ゆうた)
教育者/哲学研究者
1985年生まれ。教育者・哲学研究者で、リベラルアーツを主軸にした統合型学習塾「知窓学舎」講師。専門はウィトゲンシュタイン哲学。
デビュー著書は『世界は贈与でできている:資本主義の「すきま」を埋める倫理学』(第29回山本七平賞 奨励賞、紀伊國屋じんぶん大賞2021 第5位/2020年3月13日発売)。
久保彩(くぼ あや)
株式会社フライヤー 執行役員CCO(Chief Customer Officer)
カスタマーエンゲージメントDiv ゼネラルマネジャー
大学卒業後、大手メーカーにてシステム開発の企画・開発・PJマネジメントに携わる。その後、総合系コンサルティング・ファームで大手企業の新規事業/新規サービスの企画・立上・展開を担いながらMBAを取得。2020年よりフライヤーの新規事業担当 執行役員に就任。読書の新しい価値を追求するコミュニティflier book labo、本から深く学ぶflier book camp企画運営責任者。
2023年1月よりカスタマーサクセス責任者兼務。
2024年3月よりCCO就任。