【本記事は、OSIRO社のコミュニティ献本企画に参加し、献本を受けて執筆しました】
文学は何の役に立つのか?題名にもなっている問に平野さんは「今の世の中で正気を保つため」と冒頭で答えている。なるほど、すんなり共感して読み進めると、少年時代は「今ここ」から解放されていく感覚を文学に感じた経験にも、また共感してしまう。平野さんほどたくさんの文学を読み込んでいないにせよ、求めていた感覚が近かったことに嬉しくなってしまった。
また興味深いのが「分人」という考え方。本書でも、「分割可能な複数の人格を備えた存在」と定義し、近代の分人化について書かれている。もっとも分人化が起こりやすいのが近代の特徴としている。移動が多くなり、適応するコミュニティが細分化されるなか、分人化で適応しているからだ、と。人間の「本質としての唯一の『本当の自分』は存在しません。すべての分人が言わば『本当の自分』であり、その分人の構成と比率の変化によって、人間の『個性』は決定されます」。
『ある男』もそうだが、複数の人が同一人物を語るような小説が好きだ。だがそれも分人ということは前提とし、半分は語り手の感受性により変化するようなものだと感じていて、本当のその人はどういう人なのだろう、と様々な側面を持ちつつも包括的に構成要素のすべてを知りたくなってしまう自分がいた。本質的に平野さんの言う「分人」を理解しているのかどうか、つい自分探しをしてしまう自分を省みつつ、未読の『私とは何か』も読んでみたくなった。
本書では様々な文学についても述べられているが、阿部公房の本と共に撮影した風景のことについても触れている。撮影は(疑似的な)時間の「凍結」である。でも実際は時間は凍結せず、その風景から人は想像をめぐらす。解凍するための小説ともいえる。この話でなぜ写真を見ていて面白いのか、ストーリーが浮かんでくるのかが、わかった気がした。
多様性の時代と言われる現代、それが進んだゆえの反動なのか、どこか閉塞感も見え隠れして、ますます文学の重要性を感じさせられた。
コミュニティ献本でも様々な読み手のさらに分人たちがそれぞれに本を「解凍」し、広がりを楽しみ、文学とまた向き合う豊かな時間につなげられそうだ。
#flierbooklabo
#文学は何の役に立つのか
#平野啓一郎

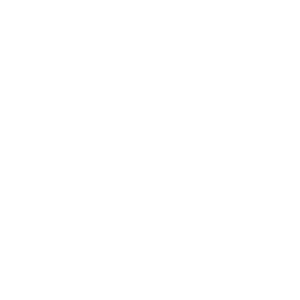
2025/07/21 22:15
